浅草といえば日本でも誰もがうなずく超有名な観光地で多くの観光客が集まる日本代表的な由緒ある名地ですよね!
そんな名地で記念の思い出に残したいのが浅草寺や周辺の下町の心地いい雰囲気ではないでしょうか!⛩️
写真にたくさんの思い出を詰めこんだり、美味しいものを食べたり、ツアーを楽しんだり盛りだくさんの記念日にする為に浅草寺のおすすめガイドラインを紹介します。
本記事では、初心者・訪日客・家族連れ・写真好き・歴史好きの方が、浅草寺(せんそうじ)を迷わず回り、やさしい導線で楽しみ、撮りたい一枚を逃さず収められます。
本記事では、
初心者・訪日客・家族連れ・写真好き・歴史好きの方が、浅草寺(せんそうじ)を迷わず回り、
やさしい導線で楽しみ、
撮りたい一枚を逃さず収められます。
昔は私も、雷門(かみなりもん)から仲見世(なかみせ)の人波に飲まれて、参拝(さんぱい)と撮影の順番で迷っていました。
この記事では「迷わない浅草寺」の考え方で、読者の気持ちに寄り添ってご案内します。
昔は私も、
雷門(かみなりもん)から仲見世(なかみせ)
の人波に飲まれて、参拝(さんぱい)と撮影の
順番で迷っていました。
この記事では「迷わない浅草寺」の考え方で、
読者の気持ちに寄り添ってご案内します。
先に結論から言いますと…
回遊の順番は「雷門 → 仲見世 → 宝蔵門(ほうぞうもん) → 本堂 → 五重塔 → 浅草神社」が最短で迷いにくい王道です。
混雑は早朝〜午前前半が穏やか。
参拝は『手水(ちょうず)→ 合掌 → 御朱印(ごしゅいん)』の3ステップ(寺院なので拍手は打ちません)。
開門・行事・授与・撮影可否は必ず公式情報で当日確認しましょう。先に結論から言いますと…
回遊の順番は
「雷門 → 仲見世 → 宝蔵門(ほうぞうもん) → 本堂 → 五重塔 → 浅草神社」が最短で迷いにくい王道です。
混雑は早朝〜午前前半が穏やか。
参拝は『手水(ちょうず)→ 合掌 → 御朱印(ごしゅいん)』の3ステップ(寺院なので拍手は打ちません)。
開門・行事・授与・撮影可否は必ず
公式情報で当日確認しましょう。
【関連記事】
昼間の浅草も下町溢れる画期ある心地いい雰囲気があり素敵な街でありますが、夜の浅草はまた違った雰囲気のある新鮮さがある街にガラリと変わって落ち着いた気持ちになります。
下記の記事はそんな夜の落ち着いた浅草の街を楽しむ為の過ごし方などを記載しましたので、良かったらお読みになってご参考にしていただけまいたら幸いです。
昼間の浅草も下町溢れる画期ある心地いい雰囲気があり素敵な街でありますが、
夜の浅草はまた違った雰囲気のある新鮮さがある街にガラリと変わって落ち着いた気持ちになります。
下記の記事は
そんな夜の落ち着いた浅草の街を楽しむ為の
過ごし方などを記載しましたので、良かったらお読みになってご参考にしていただけまいたら幸いです。

浅草に行くためのアクセスと
“迷わない”地図観
最寄り駅は“浅草駅”が基本です。
まずは雷門(かみなりもん)を目的地に設定し、直線導線で入れば迷いません。
出発前に、各社公式サイトの「出口番号」「エレベーター位置」「バリアフリー導線」を確認し、スクリーンショットで保存しておくと安心です。
出発前に、各社公式サイトの
「出口番号」「エレベーター位置」
「バリアフリー導線」を確認し、
スクリーンショットで保存しておくと安心です。
地上に出たら、Googleマップで雷門をピン留めします。
仲見世(なかみせ)を直進すれば、宝蔵門(ほうぞうもん)→本堂の順でたどり着きます。
地上に出たら、
Googleマップで雷門をピン留めします。
仲見世(なかみせ)を直進すれば、
宝蔵門(ほうぞうもん)→本堂の順で
たどり着きます。
雨の日は、屋根・ひさしのある区画をつないで移動し、撮影は近距離の“前景(ぜんけい)活用”に切り替えると快適です。
雨の日は、
屋根・ひさしのある区画をつないで移動し、
撮影は近距離の“前景(ぜんけい)活用”に
切り替えると快適です。
【関連記事】
予定している日時の天気情報は、お出かけの際に知っておきたい欠かせない情報源の一つですよね!
そんな時の為の便利なアプリなど、お役立ちになる情報を載せていますのでぜひ下記の記事を参考にしてみてください。
予定している日時の天気情報は、
お出かけの際に知っておきたい欠かせない情報源の一つですよね!
そんな時の為の便利なアプリなど、
お役立ちになる情報を載せていますので、
ぜひ下記の記事も参考にしてみてください。

最寄り駅(路線別)
- 浅草駅(東京メトロ 銀座線)。駅から雷門までが近く、初めての方は最短動線になりやすいです。
- 浅草駅(都営浅草線)。空港方面からの乗り入れが便利です。
- 浅草駅(東武スカイツリーライン)。東武利用の方にスムーズです。
- 浅草駅(つくばエクスプレス)。やや歩きますが、混雑を避けたい時の選択肢です。
雷門(Googleマップ)
浅草寺 本堂(Googleマップ)
東京メトロ 銀座線「浅草」駅|出口・エレベーター・バリアフリー
都営浅草線「浅草」駅|出口・バリアフリー
東武スカイツリーライン「浅草」駅|駅情報
つくばエクスプレス「浅草」駅|駅情報
- 浅草駅(東京メトロ 銀座線)
駅から雷門までが近く、
初めての方は最短動線になりやすいです。 - 浅草駅(都営浅草線)
空港方面からの乗り入れが便利です。 - 浅草駅(東武スカイツリーライン)
東武利用の方にスムーズです。 - 浅草駅(つくばエクスプレス)
やや歩きますが、混雑を避けたい時の
選択肢です。
【関連情報】
雷門(Googleマップ)
浅草寺 本堂(Googleマップ)
東京メトロ 銀座線「浅草」駅|出口・エレベーター・バリアフリー
都営浅草線「浅草」駅|出口・バリアフリー
東武スカイツリーライン「浅草」駅|駅情報
つくばエクスプレス「浅草」駅|駅情報
3ステップで“迷わない”入場
- 『出口とエレベーターを事前に確認』
どの路線から来ても「浅草駅」は出口が複数あります。
まず、ご利用の路線の公式サイト( 東京メトロ銀座線/ 都営浅草線/ 東武スカイツリーライン/ つくばエクスプレス )を開いて、出口番号・エレベーターの位置・バリアフリー経路をチェックし、画面をスクリーンショットしておきます。
公式ページなら乗換案内やバリアフリー設備がまとめて確認できるので、現地で迷いません。 - 『Googleマップで目的地をピン留め』
次にGoogleマップで雷門(Googleマップはこちら)を目的地に設定し、ピンを保存します。
仲見世通りを進んだ先の浅草寺本堂(Googleマップはこちら)も保存しておけば、オフラインでも迷わずに参拝ルートを確認できます。 - 『雷門をくぐったら直進』
「雷門」をくぐったら仲見世通りをまっすぐ進み、宝蔵門を抜けて本堂へ向かいます。
ルートはシンプルですが、混雑時は人の流れに合わせて進みましょう。
途中で立ち止まる場合は、通路の端に寄って他の参拝者の流れを邪魔しないようにするとスマートです。
- 『出口とエレベーターを事前に確認』
どの路線から来ても「浅草駅」は出口が複数あります。
まず、ご利用の路線を公式サイトで
( 東京メトロ銀座線)
( 都営浅草線)
(東武スカイツリーライン)
( つくばエクスプレス )
を開いて、
出口番号・エレベーターの位置・
バリアフリー経路をチェックし、
画面をスクリーンショットしておきます。
公式ページなら乗換案内やバリアフリー設備がまとめて確認できるので、現地で迷いません。 - 『Googleマップで目的地をピン留め』
次にGoogleマップで
雷門(Googleマップはこちら)
を目的地に設定し、ピンを保存します。
仲見世通りを進んだ先の
浅草寺本堂(Googleマップはこちら)
も保存しておけば、オフラインでも
迷わずに参拝ルートを確認できます。 - 『雷門をくぐったら直進』
「雷門」をくぐったら
仲見世通りをまっすぐ進み、
宝蔵門を抜けて本堂へ向かいます。
ルートはシンプルですが、混雑時は人の流れに合わせて進みましょう。
途中で立ち止まる場合は、通路の端に寄って他の参拝者の流れを邪魔しないようにするとスマートです。
まとめると…
- 駅の公式ページを開く → 出口番号・
エレベーター位置を確認してスクショ保存。 - Googleマップで「雷門」を目的地に設定 → ピン保存。
- 雷門をくぐったら直進(仲見世) → 宝蔵門 → 本堂へ。
【注意】
出口の工事・エレベーター運行・通行規制は変更される場合があります。
必ず当日は各社公式サイトの情報を最優先してください。
例:Googleマップは「浅草寺」「雷門」で検索 → 共有リンクをそのまま貼り付けてください。
公式URLは、各社公式サイト内の「駅情報」「出口案内」「バリアフリー情報」ページを指定してください。例:Googleマップは「浅草寺」「雷門」で検索 → 共有リンクをそのまま貼り付けてください。
公式URLは、各社公式サイト内の
「駅情報」「出口案内」
「バリアフリー情報」ページを
指定してください。
地上に出たら地図アプリで雷門をピン留めし、直線動線を確保します。
雨の日は屋根のある区画をつなぐルートに切り替えると快適です。
地上に出たら地図アプリで雷門をピン留めし、
直線動線を確保します。
雨の日は屋根のある区画をつなぐルートに
切り替えると快適です。
王道60分モデルコース
1)雷門:スタートで“浅草の顔”を押さえる

オリジナル画像(一部生成)
到着直後に「祈る→撮る→買う」の順で動くと迷いません。混雑が増える前に正面カットを確保。
- 正面は人が入りやすいので、3歩だけ下がって左右の柱をフレームにすると落ち着いた一枚に。
- ここでは“撮るだけ”でOK。買い物は帰路に回すと身軽です。
- 正面は人が入りやすいので、
3歩だけ下がって左右の柱をフレームにすると落ち着いた一枚に。 - ここでは“撮るだけ”でOK。
買い物は帰路に回すと身軽です。
『雷門』は浅草寺の総門で、正式名は風雷神門(ふうらいじんもん)といいます。
もともと平公雅(たいらのきんまさ)が942年に創建し、風神と雷神の像を左右に安置して伽藍を災害から守るための門でした。
その後たびたび火災で焼失し、現在の門は1960年に松下幸之助(パナソニック創業者)の寄付によって再建されたものです。
門自体は高さ約11.7メートル、幅11.4メートル、面積69.3平方メートルと堂々たる姿で、正面中央には高さ3.9メートル・幅3.3メートル・重さ約700キログラムの巨大な提灯が吊されています。
表面には「雷門」の二文字、裏面には「風雷神門」と記され、提灯は祭事の際に畳める構造になっています。
裏側には天龍・金龍の像(1978年奉安)があり、提灯の根元には彫刻の龍が隠れているので、くぐる際はぜひ見上げてみてください。
門自体は高さ約11.7メートル、幅11.4メートル、
面積69.3平方メートルと堂々たる姿で、
正面中央には高さ3.9メートル・幅3.3メートル・
重さ約700キログラムの巨大な提灯が吊されています。
表面には「雷門」の二文字、裏面には「風雷神門」と記され、提灯は祭事の際に畳める構造になっています。
裏側には天龍・金龍の像(1978年奉安)があり、
提灯の根元には彫刻の龍が隠れているので、
くぐる際はぜひ見上げてみてください。
門を抜けると仲見世通りがまっすぐ伸び、宝蔵門・本堂へと続きます。
撮影時は通行の妨げにならないよう少し横に寄り、左右の柱でフレーミングすると構図がまとまります。
風神・雷神像は右に風神、左に雷神が配置されているので、それぞれのポーズや表情にも注目です。
アクセスのポイント
- 東京メトロ銀座線「浅草駅」から徒歩約1分(出口1)。
駅の公式サイトで出口番号やエレベーター位置を事前に確認し、スクリーンショットを保存しておくと安心です。 - 都営地下鉄浅草線「浅草駅」A4出口から徒歩約2分。
- 東武スカイツリーライン「浅草駅」から徒歩約3分、つくばエクスプレス「浅草駅」から徒歩約8分。
- 雷門は浅草文化観光センターの正面にあり、Googleマップでは「雷門」で検索すると簡単に見つけられます。
※出口・バリアフリー情報は各社公式サイトを必ずご確認ください。
- 東京メトロ銀座線「浅草駅」から
徒歩約1分(出口1)。
駅の公式サイトで出口番号やエレベーター位置を事前に確認し、スクリーンショットを保存しておくと安心です。 - 都営地下鉄浅草線「浅草駅」A4出口から
徒歩約2分。 - 東武スカイツリーライン「浅草駅」から
徒歩約3分。
つくばエクスプレス「浅草駅」から徒歩約8分。 - 雷門は浅草文化観光センターの正面にあり、Googleマップでは「雷門」で検索すると簡単に見つけられます。
※出口・バリアフリー情報は
各社公式サイトを必ずご確認ください。
夜は提灯が点灯し混雑も落ち着くため、ゆっくり写真を撮りたい方は夕方以降もおすすめです。
雷門をじっくり眺めたら、仲見世通りに進んで浅草の散策を始めましょう。
夜は提灯が点灯し混雑も落ち着くため、ゆっくり
写真を撮りたい方は夕方以降もおすすめです。
雷門をじっくり眺めたら、仲見世通りに進んで浅草の散策を始めましょう。
2)仲見世:行きは“見るだけ”、帰りに買う
- 行きは人流に合わせて直進。帰路に再訪すると、荷物を持って歩き回るストレスが減ります。
- 雨天はアーケード下を繋ぐと濡れにくく快適。
仲見世(なかみせ)は雷門から宝蔵門まで約250メートル続く表参道で、江戸時代から続く国内屈指の商店街です。
東京観光公式サイトによると、通りには約90軒の店が並び、土産物や伝統工芸品、軽食などが所狭しと並んでいます。
浅草寺公式サイトでも、仲見世は日本最古の商店街の一つであり、昔ながらの玩具や菓子、各種のお土産が販売されていることが紹介されています。
仲見世(なかみせ)は
雷門から宝蔵門まで約250メートル続く表参道で、
江戸時代から続く国内屈指の商店街です。
東京観光公式サイトによると、通りには約90軒の店が並び、土産物や伝統工芸品、軽食などが所狭しと並んでいます。
浅草寺公式サイトでも、仲見世は日本最古の商店街の一つであり、昔ながらの玩具や菓子、各種のお土産が販売されていることが紹介されています。
仲見世は昼は大変賑わい、江戸情緒漂う景観の中で木履(げた)やこけし人形、和雑貨から流行のバッグまで多彩な品を手にできます。
夜になると、閉店後のシャッターに描かれた絵巻物風の壁画が現れ、昼間とは違う表情を見せてくれます。
行きは「見るだけ」、帰りに買う
仲見世は道幅が狭く人通りが多いので、行きは“見るだけ”にして、手ぶらで本堂まで進むのがおすすめです。
先に参拝を済ませることで身軽に行動でき、帰り道にゆっくり買い物を楽しめます。
特に中盤から終盤にかけては混雑が増すため、商品を手に持ちながら歩くと周囲の人の流れを妨げやすくなります。
なので、お土産は帰路でまとめて購入すると道中楽に行動できると思いますのでおすすめです。
仲見世は道幅が狭く人通りが多いので、
行きは“見るだけ”にして、
手ぶらで本堂まで進むのがおすすめです。
先に参拝を済ませることで身軽に行動でき、
帰り道にゆっくり買い物を楽しめます。
特に中盤から終盤にかけては混雑が増すため、
商品を手に持ちながら歩くと周囲の人の流れを
妨げやすくなります。
なので、お土産は帰路でまとめて購入すると道中楽に行動できると思いますのでおすすめです。
散策のポイント
- 『江戸の雰囲気を満喫』
江戸期の門前町の賑わいを再現した通りで、和風の店構えや提灯、緑瓦の屋根が続きます。 - 『商品ジャンル』
和菓子(雷おこし、芋羊羹)、人形焼、扇子、箸、着物や浴衣、木履、こけしなど伝統的な品から、最近人気のアネロバッグや雑貨まで幅広い品揃えに思わず目移りしてしまいながらもそのひと時こそ楽しい瞬間ですよね。 - 『時間帯選び』
通りは午前10時頃から開店し、夕方19時頃に閉店する店が多いですが、店により前後します。
早朝は人が少なく散策しやすく、夜はシャッターアートが見どころです。 - 『マナーと混雑回避』
歩きながらの飲食は周囲の迷惑になるため、店先や路肩で食べ終えてから歩き始めるとスマートです。
混雑が辛い場合は仲見世の裏通り(東西の路地)に回ると人が少なく、カフェや小さな店が点在しているので休憩しやすいです。
- 『江戸の雰囲気を満喫』
江戸期の門前町の賑わいを再現した通りで、
和風の店構えや提灯、緑瓦の屋根が続きます。 - 『商品ジャンル』
和菓子(雷おこし、芋羊羹)、人形焼、扇子、箸、着物や浴衣、木履、こけしなど伝統的な品から、最近人気のアネロバッグや雑貨まで
幅広い品揃えに思わず目移りしてしまいながらもそのひと時こそ楽しい瞬間ですよね。 - 『時間帯選び』
通りは午前10時頃から開店し、夕方19時頃に
閉店する店が多いですが、店により前後します。
早朝は人が少なく散策しやすく、
夜はシャッターアートが見どころです。 - 『マナーと混雑回避』
歩きながらの飲食は周囲の迷惑になるため、
店先や路肩で食べ終えてから歩き始めると
スマートです。
混雑が辛い場合は
仲見世の裏通り(東西の路地)に回ると人が
少なく、カフェや小さな店が点在しているので
休憩しやすいです。
このように、仲見世は浅草の歴史と今を感じられる特別な通りです。
まずは本堂で参拝して身軽になり、帰り道でお気に入りのお土産をゆっくり選んでみてください。
このように、仲見世は
浅草の歴史と今を感じられる特別な通りです。
まずは本堂で参拝して身軽になり、帰り道でお気に入りのお土産をゆっくり選んでみてください。
3)宝蔵門:縦位置×対称が映える

オリジナル画像(一部生成)
宝蔵門は二重構造の大門。縦位置で中央を正面から捉え、左右の柱をフレームにすると対称構図が美しく決まります。
宝蔵門は二重構造の大門。
縦位置で中央を正面から捉え、左右の柱をフレームにすると対称構図が美しく決まります。
宝蔵門は浅草寺の内門で、正式には『宝蔵門(ほうぞうもん)』と呼ばれます。
942年に武将の平公雅(たいらのきんまさ)が建立したのが始まりで、その後、徳川家光が1649年に新たな門を建てました。
現在の門は1964年に大谷米太郎(ホテルニューオータニ創業者)の寄付によって再建されたものです。
宝蔵門は浅草寺の内門で、
正式には『宝蔵門(ほうぞうもん)』と呼ばれます。
942年に武将の平公雅(たいらのきんまさ)
が建立したのが始まりで、その後、
徳川家光が1649年に新たな門を建てました。
現在の門は1964年に
大谷米太郎(ホテルニューオータニ創業者)
の寄付によって再建されたものです。
この門は「宝蔵」という名の通り、火災に強い構造で寺宝を保管する役割も担っています。
高さ約22.7メートル、幅21メートル、奥行き8メートルの二重の楼門で、仲見世通りの北端にそびえる姿は圧巻です。
左右には迫力ある仁王像が立ち、かつては「仁王門」と呼ばれていました。
この門は「宝蔵」という名の通り、火災に強い構造で寺宝を保管する役割も担っています。
高さ約22.7メートル、幅21メートル、
奥行き8メートルの二重の楼門で、
仲見世通りの北端にそびえる姿は圧巻です。
左右には迫力ある仁王像が立ち、
かつては「仁王門」と呼ばれていました。
門内には3つの大きな提灯が吊されており、中央の提灯は高さ約3.75メートル・幅約2.7メートル、重さ450キログラムで、2014年に東京都中央区小舟町から寄進されました。
また、裏側には巨大なわらじが2枚掛けられており、その大きさ(高さ約4.5メートル、幅1.5メートル、重さ500キログラム)が仁王の力強さを示し、魔除けの意味が込められています。
門内には3つの大きな提灯が吊されており、
中央の提灯は高さ約3.75メートル・
幅約2.7メートル、重さ450キログラムで、
2014年に東京都中央区小舟町から寄進されました。
また、裏側には巨大なわらじが2枚掛けられており、その大きさ(高さ約4.5メートル、幅1.5メートル、重さ500キログラム)が仁王の力強さを示し、
魔除けの意味が込められています。
撮影のポイント
- 『縦位置×対称』
宝蔵門の魅力は左右対称の構造です。門の正面に立ち、縦位置で撮ると二本の柱と中央の提灯がきれいに収まり、奥行きも強調されます。 - 『前景を活用』
手前の提灯や柱を前景に入れて、奥の五重塔まで見通す三層構図にすると奥行き感が出ます。 - 『夜のライトアップ』
夕方以降はライトアップされ、人通りも減るため、静かな雰囲気で撮影できます。
提灯の赤と暗い空の対比が美しい一枚になります。 - 『撮影時のマナー』
参拝者の導線を塞がないよう、通路の端に寄って短時間で撮影を済ませましょう。
- 『縦位置×対称』
宝蔵門の魅力は左右対称の構造です。
門の正面に立ち、縦位置で撮ると
二本の柱と中央の提灯がきれいに収まり、
奥行きも強調されます。 - 『前景を活用』
手前の提灯や柱を前景に入れて、
奥の五重塔まで見通す
三層構図にすると奥行き感が出ます。 - 『夜のライトアップ』
夕方以降はライトアップされ、
人通りも減るため、
静かな雰囲気で撮影できます。
提灯の赤と暗い空の対比が
美しい一枚になります。 - 『撮影時のマナー』
参拝者の導線を塞がないよう、
通路の端に寄って
短時間で撮影を済ませましょう。
宝蔵門をくぐると浅草寺の本堂が正面に、左手には五重塔が見えます。
写真を撮った後は、参拝や本堂の鑑賞へと進みましょう。
歴史の重みと現代の技術が融合したこの門は、浅草寺の中でも見応えのあるスポットです。
宝蔵門をくぐると浅草寺の本堂が正面に、
左手には五重塔が見えます。
写真を撮った後は、
参拝や本堂の鑑賞へと進みましょう。
歴史の重みと現代の技術が融合したこの門は、
浅草寺の中でも見応えのあるスポットです。
4)本堂:参拝を先に、撮影は後で


オリジナル画像(一部生成)
・寺院は拍手なし。
・静かに合掌を。
混雑時は先に祈り、落ち着いてから撮影が快適です。
参拝は「手水 → 合掌 → お賽銭」の順が安心です。
御朱印の場所・受付時間・初穂料(はつほりょう)は公式案内で当日確認を。
本堂は観音堂(かんのんどう)とも呼ばれ、徳川家光により建立されて国宝に指定されていましたが、1945年の東京大空襲で焼失し、1958年に全国の信者からの寄付で再建されました。
屋根は他の寺院と比べても大きく反り返った斜面が特徴で、外から眺めるだけでも堂々とした美しさがあります。
本堂は観音堂(かんのんどう)とも呼ばれ、
徳川家光により建立されて国宝に指定されていましたが、1945年の東京大空襲で焼失し、1958年に全国の信者からの寄付で再建されました。
屋根は他の寺院と比べても大きく反り返った斜面が特徴で、外から眺めるだけでも堂々とした美しさがあります。
内部は内陣(ないじん)と外陣(げじん)に分かれ、内陣中央には浅草寺のご本尊である観音菩薩が安置されています。
このご本尊は645年から非公開とされ、僧侶でさえ見ることができない秘仏として守られてきました。
外陣には、江戸時代の名書家・野口雨停(のぐち せっこう)による書が奉納されており、観音の慈悲を表現した言葉が大きなお賽銭箱の左右に掲げられています。
内部は内陣(ないじん)と外陣(げじん)
に分かれ、内陣中央には浅草寺のご本尊である
観音菩薩が安置されています。
このご本尊は645年から非公開とされ、
僧侶でさえ見ることができない秘仏として
守られてきました。
外陣には、
江戸時代の名書家・野口雨停(のぐち せっこう)
による書が奉納されており、
観音の慈悲を表現した言葉が
大きなお賽銭箱の左右に掲げられています。
参拝の流れ
- 『手水で浄める』
本堂手前の手水舎で柄杓(ひしゃく)を使い、左手・右手・口を順に清めます。 - 『合掌して祈る』
本堂前で軽く頭を下げ、お賽銭をそっと入れたら、静かに合掌して心の中で願いごとを伝えます。
浅草寺では拍手は打ちません。
公式サイトによると、「Namu Kanzeon Bosatsu(南無観世音菩薩)」と唱えるのが基本です。 - 『御朱印やお守り』
祈りを終えたら、境内の授与所で御朱印やお守りを受けることができます。
受付時間や初穂料は日によって異なるため、必ず現地の案内や公式サイトで確認してください。
- 『手水で浄める』
本堂手前の手水舎で柄杓(ひしゃく)を使い、
左手・右手・口を順に清めます。 - 『合掌して祈る』
本堂前で軽く頭を下げ、お賽銭をそっと入れたら、静かに合掌して心の中で願いごとを伝えます。
浅草寺では拍手は打ちません。
公式サイトによると、
「Namu Kanzeon Bosatsu(南無観世音菩薩)」と唱えるのが基本です。 - 『御朱印やお守り』
祈りを終えたら、境内の授与所で
御朱印やお守りを受けることができます。
受付時間や初穂料は日によって異なるため、
必ず現地の案内や公式サイトで確認してください。
撮影のポイントと注意
- 『祈りを済ませてから』
本堂前は参拝者が絶えず行き来します。
先に参拝を済ませ、階段から少し離れた位置に移動して撮影すれば、他の人の流れを妨(さまた)げません。 - 『外観は斜めが狙い目』
本堂の大きな屋根や正面の造りを収めるには、やや斜めから全体を捉えると立体感が出ます。
香炉の煙を前景にすると雰囲気が増します。 - 『内部の撮影は控える』
本堂内は神聖な場所です。
多くの寺院と同様に、堂内での撮影は制限されている場合があります。
表示や係員の指示に従い、周囲への配慮を忘れずに。 - 『開門時間をチェック』
本堂は6:00〜17:00(10月〜3月は6:30〜17:00)まで開いています。
早朝は参拝者が少ないのでゆったり見学できます。
- 『祈りを済ませてから』
本堂前は参拝者が絶えず行き来します。
先に参拝を済ませ、階段から少し離れた位置に
移動して撮影すれば、
他の人の流れを妨(さまた)げません。 - 『外観は斜めが狙い目』
本堂の大きな屋根や正面の造りを収めるには、
やや斜めから全体を捉えると立体感が出ます。
香炉の煙を前景にすると雰囲気が増します。 - 『内部の撮影は控える』
本堂内は神聖な場所です。
多くの寺院と同様に、
堂内での撮影は制限されている場合があり
ます。
表示や係員の指示に従い、
周囲への配慮を忘れずに。 - 『開門時間をチェック』
本堂は6:00〜17:00(10月〜3月は6:30〜17:00)まで開いています。
早朝は参拝者が少ないのでゆったり見学できます。
本堂前には大きな香炉があり、参拝者が線香の煙を浴びて無病息災を祈っています。
香炉越しに本堂を撮ると臨場感のある写真になる一方、煙の量が多い日はカメラやスマートフォンが灰で汚れやすいので注意が必要です。
参拝を終えたら、外陣の柱や屋根の装飾をじっくり観察してみましょう。
重厚な建築美と信仰の歴史を感じることができます。
本堂前には大きな香炉があり、参拝者が線香の煙を浴びて無病息災を祈っています。
香炉越しに本堂を撮ると臨場感のある写真になる
一方、煙の量が多い日はカメラやスマートフォンが灰で汚れやすいので注意が必要です。
参拝を終えたら、外陣の柱や屋根の装飾をじっくり観察してみましょう。
重厚な建築美と信仰の歴史を感じることができます。
5)五重塔:時間帯で“撮り方”を変える


オリジナル画像(一部生成)
五重塔は高さ約53メートルの堂々とした塔で、1973年に再建されました。
朝・昼・夜で表情が変わるので、撮影ポイントを時間帯ごとに工夫しましょう。
五重塔は高さ約53メートルの堂々とした塔で、
1973年に再建されました。
朝・昼・夜で表情が変わるので、
撮影ポイントを時間帯ごとに工夫しましょう。
浅草寺の五重塔は、1973年(昭和48年)に鉄骨・鉄筋コンクリート造りで再建された美しい塔です。
その基壇は塔院と呼ばれる建物の上にあり、外からは地面に建っているように見えますが、実際は土台が一段高くなっています。
塔の高さは地上から約53メートル(塔身のみ48.32メートル)あり、東京で二番目に高い五重塔として知られています。
浅草寺の五重塔は、1973年(昭和48年)に鉄骨・
鉄筋コンクリート造りで再建された美しい塔です。
その基壇は塔院と呼ばれる建物の上にあり、
外からは地面に建っているように見えますが、
実際は土台が一段高くなっています。
塔の高さは地上から
約53メートル(塔身のみ48.32メートル)あり、
東京で二番目に高い五重塔として知られています。
五重塔の起源はインドのストゥーパ(仏塔)にあり、浅草寺でも最上層にはスリランカのイスルムニヤ寺院から奉戴した仏舎利(ぶっしゃり:釈迦の遺骨)が納められています。
最初の塔は天慶5年(942年)に平公雅が建立したと伝えられ、江戸時代には徳川家光が再建した五重塔が本堂の東側にそびえていました。
しかし、1945年の東京大空襲で焼失し、現在の塔は全国の信徒からの寄進で再建されたものです。
五重塔の起源はインドのストゥーパ(仏塔)
にあり、浅草寺でも最上層には
スリランカのイスルムニヤ寺院から奉戴した
仏舎利(ぶっしゃり:釈迦の遺骨)
が納められています。
最初の塔は天慶5年(942年)に平公雅が建立したと伝えられ、江戸時代には徳川家光が再建した五重塔が本堂の東側にそびえていました。
しかし、1945年の東京大空襲で焼失し、現在の塔は全国の信徒からの寄進で再建されたものです。
時間帯別の撮り方
- 『朝(早朝)』
参拝者が少ない時間帯は、正面から縦位置で全景を捉えるチャンスです。
柔らかい朝の光で朱色の塔身が映え、塔のシルエットと青空のコントラストが美しく写ります。 - 『昼(昼前〜午後)』
太陽が高い時間帯は、塔の陰影が強くなり、屋根の重なりや細部の造形が際立ちます。
斜めから撮影して奥行きを演出したり、周囲の木々や本堂を前景に入れて立体感を出すのがおすすめです。 - 『夜(ライトアップ)』
浅草寺では日没から午後11時頃まで毎日ライトアップが行われています。
暗闇に浮かび上がる朱色の塔は幻想的で、背景の夜空やスカイツリーとのコントラストが楽しめます。
露出を調整し、少し暗めに撮ると塔の灯りが引き立ちます。
- 『朝(早朝)』
参拝者が少ない時間帯は、
正面から縦位置で全景を捉えるチャンスです。
柔らかい朝の光で朱色の塔身が映え、
塔のシルエットと青空のコントラストが
美しく写ります。 - 『昼(昼前〜午後)』
太陽が高い時間帯は、塔の陰影が強くなり、
屋根の重なりや細部の造形が際立ちます。
斜めから撮影して奥行きを演出したり、
周囲の木々や本堂を前景に入れて
立体感を出すのがおすすめです。 - 『夜(ライトアップ)』
浅草寺では
日没から午後11時頃まで毎日ライトアップ
が行われています。
暗闇に浮かび上がる朱色の塔は幻想的で、
背景の夜空やスカイツリーとのコントラストが楽しめます。
露出を調整し、
少し暗めに撮ると塔の灯りが引き立ちます。
撮影マナーとコツ
- 『参拝を優先』
五重塔周辺は本堂へ向かう参拝動線の途中にあり、周囲には霊牌殿や寺務所があります。
撮影に夢中になって通行の妨げにならないよう、通路の端に寄って短時間で撮影しましょう。 - 『前景を活用』
宝蔵門や灯籠、緑の樹木を前景に入れると、塔の高さや奥行きを強調できます。
スマホの場合は望遠2×〜3×を使うと背景を圧縮して人混みが目立ちにくくなります。 - 『公式情報をチェック』
塔院は通常非公開ですが、年に数回(例:釈尊の三聖日や永代供養法要など)参拝できる日があります。
見学や内部参拝を希望する場合は浅草寺公式サイトで最新情報をご確認ください。
- 『参拝を優先』
五重塔周辺は本堂へ向かう参拝動線の途中に
あり、周囲には霊牌殿や寺務所があります。
撮影に夢中になって通行の妨げにならないよう、通路の端に寄って短時間で撮影しましょう。 - 『前景を活用』
宝蔵門や灯籠、緑の樹木を前景に入れると、
塔の高さや奥行きを強調できます。
スマホの場合は望遠2×〜3×を使うと背景を
圧縮して人混みが目立ちにくくなります。 - 『公式情報をチェック』
塔院は通常非公開ですが、
年に数回
(例:釈尊の三聖日や永代供養法要など)
参拝できる日があります。
見学や内部参拝を希望する場合は浅草寺公式サイトで最新情報をご確認ください。
朱色の五重塔は、時間帯や天気によってさまざまな表情を見せる浅草のシンボルです。
朝の静けさや夜のライトアップなど、自分の好きな雰囲気で写真を撮って、浅草寺参拝の思い出に残してください。
朱色の五重塔は、時間帯や天気によって
さまざまな表情を見せる浅草のシンボルです。
朝の静けさや夜のライトアップなど、
自分の好きな雰囲気で写真を撮って、
浅草寺参拝の思い出に残してください。
6)浅草神社:静かな余白で一息
- 本堂の賑わいから一歩離れ、静かな時間を確保。
- ここで休憩してから、仲見世に戻って買い物がスムーズです。
浅草神社は、浅草寺の東側にある神社で、『檜前浜成(ひのくまのはまなり)』・『檜前武成(たけなり)』の漁師兄弟と、観音像を見つけた彼らの恩人『土師真中知(はじのまなかち)』の三人を祀って(まつって)います。
推古天皇の時代、兄弟が隅田川で投網を引いた際に観音像を引き上げ、土師真中知がこれを観音菩薩と見抜いて祀った(まつった)ことが浅草寺の起源となりました。
後世、三人の功績を讃えるために「三社権現社」が創建され、それが浅草神社の始まりです。
浅草神社は、浅草寺の東側にある神社で、
『檜前浜成(ひのくまのはまなり)』・
『檜前武成(たけなり)』の漁師兄弟と、観音像を見つけた彼らの恩人『土師真中知(はじのまなかち)』の三人を祀って(まつって)います。
推古天皇の時代、兄弟が隅田川で投網を引いた際に観音像を引き上げ、土師真中知がこれを観音菩薩と見抜いて祀った(まつった)ことが浅草寺の起源となりました。
後世、三人の功績を讃えるために「三社権現社」が創建され、それが浅草神社の始まりです。
現在の社殿は第三代将軍・徳川家光が慶安2年(1649年)に寄進した権現造(ごんげんづくり)の建物で、本殿・幣殿・拝殿が渡り廊下で結ばれています。
350年以上にわたり火災や戦災、関東大震災などを免れて当時の姿を保ち、1951年には国の重要文化財に指定されました。
1996年には彩色とうるしを塗り直して鮮やかな姿を取り戻しています。
現在の社殿は第三代将軍・徳川家光が慶安2年(1649年)に寄進した権現造(ごんげんづくり)の建物で、本殿・幣殿・拝殿が渡り廊下で結ばれています。
350年以上にわたり火災や戦災、関東大震災などを
免れて当時の姿を保ち、1951年には国の重要文化財に指定されました。
1996年には彩色とうるしを塗り直して鮮やかな姿を取り戻しています。
参拝と散策のポイント
- 『静かな環境』
浅草神社は浅草寺の喧騒から少し離れており、境内にはベンチや木陰もあってゆっくりと休憩できます。
大きな木々に囲まれた敷地で深呼吸をすると、都会の真ん中にいることを忘れそうです。 - 『社殿の造りを観察』
権現造りの社殿は、日光東照宮と同じ様式で豪華な彫刻や彩色が見どころです。
細部をじっくり眺めると、龍や霊獣など縁起の良いモチーフが随所に施されています。 - 『境内の見どころ』
境内には明治18年建立の「神明鳥居」、参拝前に身を清める「手水舎」、ご祭神ゆかりの槐(えんじゅ)の木を祀った(まつった)「神木」があります。
また、三社祭で担がれる一之宮・二之宮・三之宮の宮神輿を収める「神輿庫」や、神楽や舞を奉納する「神楽殿」も必見です。
江戸初期作の珍しい「夫婦狛犬」は良縁や夫婦円満のご利益があるとされています。 - 『御朱印・御守』
浅草神社でも御朱印や御守がいただけます。
受付時間や授与品の種類は公式サイトを参照の上、静かな境内でゆっくりと選びましょう。
- 『静かな環境』
浅草神社は浅草寺の喧騒から少し離れており、
境内にはベンチや木陰もあってゆっくりと
休憩できます。
大きな木々に囲まれた敷地で深呼吸をすると、都会の真ん中にいることを忘れそうです。 - 『社殿の造りを観察』
権現造りの社殿は、日光東照宮と同じ様式で
豪華な彫刻や彩色が見どころです。
細部をじっくり眺めると、龍や霊獣など縁起の
良いモチーフが随所に施されています。 - 『境内の見どころ』
境内には明治18年建立の「神明鳥居」、
参拝前に身を清める「手水舎」、
ご祭神ゆかりの槐(えんじゅ)の木を
祀った(まつった)「神木」があります。
また、三社祭で担がれる一之宮・二之宮・三之宮の宮神輿を収める「神輿庫」や、神楽や舞を奉納する「神楽殿」も必見です。
江戸初期作の珍しい「夫婦狛犬」は
良縁や夫婦円満のご利益があるとされています。 - 『御朱印・御守』
浅草神社でも御朱印や御守がいただけます。
受付時間や授与品の種類は
公式サイトを参照の上、
静かな境内でゆっくりと選びましょう。
参拝は、浅草寺での参拝を終えた後に足を運ぶのがおすすめです。
雷門や仲見世の賑わいから少し距離を置き、静かな余白で心を整える時間が持てます。
三人の恩人に感謝を捧げながら、浅草の歴史に思いを馳せてみてください。
参拝は、浅草寺での参拝を終えた後に
足を運ぶのがおすすめです。
雷門や仲見世の賑わいから少し距離を置き、
静かな余白で心を整える時間が持てます。
三人の恩人に感謝を捧げながら、
浅草の歴史に思いを馳せてみてください。
寺と神社の作法ちがい超入門
浅草寺は寺院です。拍手は打たず、静かに合掌するのが一般的です。
浅草寺は寺院です。
拍手は打たず、静かに合掌するのが一般的です。
- 『手水(ちょうず)』
柄杓(ひしゃく)は“手→口→手→柄”の順で軽く清めます。 - 『本堂』
ゆっくり一礼→合掌。
撮影の可否は掲示に従うのがルール。 - 『御朱印』
授与所の案内と受付時間を確認。
列が長い時は先に番号札/書置き対応になる場合があります。
撮影は参拝の妨げにならないこと。
三脚の使用や大声の呼びかけ、通路での長時間の占有は避けます。撮影は参拝の妨げにならないこと。
三脚の使用や大声の呼びかけ、
通路での長時間の占有は避けます。
寺と神社の作法ちがい
仏教の寺と神道の神社では、参拝方法や礼儀作法が異なります。
ここでは浅草寺と浅草神社を例に、初めての方でも分かりやすいように基本の作法をまとめました。
仏教の寺と神道の神社では、
参拝方法や礼儀作法が異なります。
ここでは浅草寺と浅草神社を例に、初めての方でも分かりやすいように基本の作法をまとめました。
まず知っておきたい違い
- 『祈り方』
寺では、手を合わせて静かに合掌し、心の中で願いを唱えます。
浅草寺では『南無観世音菩薩(なむかんぜおんぼさつ)』と唱えるのが基本です。
一方、神社では拝礼と拍手(はくしゅ、かしわで)が含まれるのが一般的です。
鳥居の内側は神域とされるため、入る前に軽く一礼をしてから進み、参拝前に手水舎で両手と口を清めます。 - 『入口の違い』
神社には神域と俗界を区切る鳥居があります。
浅草神社の鳥居は「神明鳥居」という形式で、明治18年に建立されました。
寺院には門(山門)があり、くぐる前に合掌して軽く一礼するのが礼儀です。 - 『浄め方』
神社では手水舎で両手と口を濯ぎ、心身を清めます。
寺院でも同様に手水舎があれば浄めますが、合掌の作法に続く礼拝で拍手は打ちません。
- 『祈り方』
寺では、手を合わせて静かに合掌し、
心の中で願いを唱えます。
浅草寺では
『南無観世音菩薩(なむかんぜおんぼさつ)』
と唱えるのが基本です。
一方、神社では
拝礼と拍手(はくしゅ、かしわで)
が含まれるのが一般的です。
鳥居の内側は神域とされるため、
入る前に軽く一礼をしてから進み、
参拝前に手水舎で両手と口を清めます。 - 『入口の違い』
神社には神域と俗界を区切る鳥居があります。
浅草神社の鳥居は「神明鳥居」という形式で、
明治18年に建立されました。
寺院には門(山門)があり、
くぐる前に合掌して軽く一礼するのが礼儀です。 - 『浄め方』
神社では手水舎で両手と口を濯ぎ、
心身を清めます。
寺院でも同様に手水舎があれば浄めますが、
合掌の作法に続く礼拝で拍手は打ちません。
浅草寺(寺院)の基本作法
- 『手水を取る』
左手→右手→口→柄杓の順に清めます。 - 『本堂で祈る』
お賽銭をそっと入れ、軽く一礼して合掌します。
浅草寺では『南無観世音菩薩(なむかんぜおんぼさつ)』と唱えるのが伝統。 - 『拍手は打たない』
寺院は仏教施設のため、祈りの際に拍手を打つ作法はありません。
- 『手水を取る』
左手→右手→口→柄杓の順に清めます。 - 『本堂で祈る』
お賽銭をそっと入れ、軽く一礼して合掌します。
浅草寺では
『南無観世音菩薩(なむかんぜおんぼさつ)』
と唱えるのが伝統。 - 『拍手は打たない』
寺院は仏教施設のため、
祈りの際に拍手を打つ作法はありません。
浅草神社(神社)の基本作法
- 『鳥居をくぐる前に一礼』
鳥居は神域への入口を示し、軽く頭を下げてからくぐります。 - 『手水で浄める』
参拝前に手水舎の水で両手と口を清めます。 - 『拝礼と柏手』
一般的には二回深くお辞儀をし、胸の高さで手を合わせて柏手(かしわで)を打ち、最後にもう一度お辞儀をします。
神社によって拍手の回数が異なる場合もあるので、境内の案内や神職の指示に従ってください。
- 『鳥居をくぐる前に一礼』
鳥居は神域への入口を示し、
軽く頭を下げてからくぐります。 - 『手水で浄める』
参拝前に手水舎の水で両手と口を清めます。 - 『拝礼と柏手』
一般的には二回深くお辞儀をし、
胸の高さで手を合わせて柏手(かしわで)
を打ち、最後にもう一度お辞儀をします。
神社によって拍手の回数が異なる場合もあるので、境内の案内や神職の指示に従ってください。
寺と神社では祈り方や礼儀が異なりますが、共通して大切なのは静かな心で神仏に向き合い、境内の掲示や案内に従って丁寧に参拝することです。
迷ったときは近くの案内板や神職・僧侶に尋ねると安心です。
寺と神社では祈り方や礼儀が異なりますが、
共通して大切なのは
静かな心で神仏に向き合い、境内の掲示や案内に
従って丁寧に参拝することです。
迷ったときは近くの案内板や神職・
僧侶に尋ねると安心です。
撮る浅草寺:
前景の和小物で“整う一枚”
人が多い浅草寺では、前景(ぜんけい)に暖簾・提灯・瓦・格子など“和の小物”を入れて、主役(門・本堂・塔)を奥に配置すると、三層構図で画面が整います。
人が多い浅草寺では、前景(ぜんけい)に
暖簾・提灯・瓦・格子など“和の小物”を入れて、
主役(門・本堂・塔)を奥に配置すると、
三層構図で画面が整います。
スマホ3Tips
- 露出ロック:主役で長押し→明るさを微調整(白飛びを防ぐ)。
- 望遠側に切替:雑然とした背景を圧縮して整理。
- 斜めから“前景→主役→奥”で奥行きを作る。
前景の和小物で“整う一枚”
浅草寺の境内や仲見世には、古き良き日本を感じさせる和小物があふれています。
仲見世では扇子や人形焼、飴細工、和雑貨など「伝統的な日本のおもちゃや菓子、土産品」が販売されており、門前には巨大な提灯やわらじ、仁王像などが立ち並びます。
これらのアイテムを前景に取り入れると、写真に奥行きと物語性が生まれ、浅草らしい風情が際立ちます。
浅草寺の境内や仲見世には、
古き良き日本を感じさせる和小物があふれています。
仲見世では扇子や人形焼、飴細工、和雑貨など
「伝統的な日本のおもちゃや菓子、土産品」が
販売されており、門前には巨大な提灯やわらじ、
仁王像などが立ち並びます。
これらのアイテムを前景に取り入れると、
写真に奥行きと物語性が生まれ、
浅草らしい風情が際立ちます。
和小物を活かす構図のポイント
- 『前景・中景・奥景の三層構図』
手前に提灯や扇子などの和小物を配置し、中央に門や本堂、奥に五重塔や青空を入れると画面に奥行きが生まれます。
被写体にピントを合わせ、前景はややぼかすと主役が引き立ちます。 - 『左右対称の門を額縁に』
宝蔵門や雷門の朱塗りの柱や大提灯を“額縁”として使い、中央奥に本堂や五重塔を置くと、バランスの良い一枚になります。
縦位置で撮ると高さと奥行きが強調されます。 - 『売り物も前景として楽しむ』
仲見世の屋台に並ぶ飴細工や扇子、木靴などは色とりどりで、浅草の雰囲気を伝える絶好の素材です。
店先の賑わいを前景に入れると、写真にストーリーが生まれます。 - 『時間帯で光を味方に』
早朝は柔らかい光で影が弱く、色彩が鮮やかに出ます。
昼は強い光で陰影がはっきりし、五重塔の瓦の重なりが美しく見えます。
夕方や夜はライトアップにより提灯や門が浮かび上がり、幻想的な雰囲気になります。 - 『人流に配慮した撮影』
参拝者の通行を妨げないよう、撮影は通路の端で手短に。
三脚は混雑時には使用を控え、スマートフォンや軽量カメラで撮影するのがスマートです。
- 『前景・中景・奥景の三層構図』
手前に提灯や扇子などの和小物を配置し、
中央に門や本堂、奥に五重塔や青空を入れると画面に奥行きが生まれます。
被写体にピントを合わせ、
前景はややぼかすと主役が引き立ちます。 - 『左右対称の門を額縁に』
宝蔵門や雷門の朱塗りの柱や大提灯を“額縁”
として使い、中央奥に本堂や五重塔を置くと、バランスの良い一枚になります。
縦位置で撮ると高さと奥行きが強調されます。 - 『売り物も前景として楽しむ』
仲見世の屋台に並ぶ飴細工や扇子、木靴などは色とりどりで、
浅草の雰囲気を伝える絶好の素材です。
店先の賑わいを前景に入れると、
写真にストーリーが生まれます。 - 『時間帯で光を味方に』
早朝は柔らかい光で影が弱く、
色彩が鮮やかに出ます。
昼は強い光で陰影がはっきりし、
五重塔の瓦の重なりが美しく見えます。
夕方や夜はライトアップにより
提灯や門が浮かび上がり、幻想的な雰囲気に
なります。 - 『人流に配慮した撮影』
参拝者の通行を妨げないよう、
撮影は通路の端で手短に。
三脚は混雑時には使用を控え、
スマートフォンや軽量カメラで
撮影するのがスマートです。
構図例:雷門・仲見世・宝蔵門
例えば、雷門では巨大な大提灯と左右の柱をフレームに、本堂や五重塔を奥に入れる“額縁構図”がおすすめです。
仲見世では前景に華やかな和雑貨を入れ、中央に賑わう人の流れ、奥に宝蔵門を収めることで、歩く視線の流れをそのまま写真に表現できます。
宝蔵門では二層構造の門と大きな提灯、背後の五重塔を三層構図で組み合わせると、浅草寺の奥行きと高さが伝わる一枚になります。
例えば、雷門では巨大な大提灯と左右の柱を
フレームに、本堂や五重塔を奥に入れる
“額縁構図”がおすすめです。
仲見世では前景に華やかな和雑貨を入れ、
中央に賑わう人の流れ、奥に宝蔵門を
収めることで、
歩く視線の流れをそのまま写真に表現できます。
宝蔵門では二層構造の門と大きな提灯、
背後の五重塔を三層構図で組み合わせると、
浅草寺の奥行きと高さが伝わる一枚になります。
浅草寺には撮影禁止エリアもあります。
境内の掲示や係員の指示に従い、参拝を優先した上で撮影を楽しみましょう。
周囲への配慮を忘れずに、和小物と歴史的建造物が織りなす浅草ならではの景色を収めてください。
浅草寺には撮影禁止エリアもあります。
境内の掲示や係員の指示に従い、
参拝を優先した上で撮影を楽しみましょう。
周囲への配慮を忘れずに、和小物と歴史的建造物が織りなす浅草ならではの景色を収めてください。
アクセシビリティと安心ポイント
- 足元:雨の日は石畳が滑りやすい区画あり。屋根のある通路を繋いで移動。
- ベビーカー:人流の切れ目で一旦待避→再合流のリズムが安全。
- 休憩:本堂〜浅草神社で一息→仲見世で再合流。小さなお子さまは早朝が快適。
- トイレ・エレベーター:位置は現地掲示・公式で最新確認。スクショ保存が安心。
- 『足元』
雨の日は石畳が滑りやすい区画あり。
屋根のある通路を繋いで移動。 - 『ベビーカー』
人流の切れ目で一旦待避→再合流のリズムが安全。 - 『休憩』
本堂〜浅草神社で一息→仲見世で再合流。
小さなお子さまは早朝が快適。 - 『トイレ・エレベーター』
位置は現地掲示・公式で最新確認。
スクショ保存が安心。
みくじ売り場とおまもり・御朱印
浅草寺の境内には、願いごとを占うみくじ売り場や、参拝記念の御朱印、さまざまなお守りを授与する所があります。
ここでは、それぞれの基本的な受け方やマナーを紹介します。
浅草寺の境内には、
願いごとを占うみくじ売り場や、
参拝記念の御朱印、
さまざまなお守りを授与する所があります。
ここでは、
それぞれの基本的な受け方やマナーを紹介します。
みくじ:観音百籤(かんのんひゃくせん)

オリジナル画像(一部生成)
みくじ売り場は本堂西側の授与所近くにあります。
番号の書かれた棒を引き、同じ番号の引き出しからおみくじを取り出します。
浅草寺のおみくじは、平安時代の高僧・良源が比叡山延暦寺で始めた占いを伝えたとされる『観音百籤(ひゃくせん)』というスタイルです。
凶(悪い運勢)が出やすいと言われることがありますが、これは昔ながらの配分を守っているためで、特別に凶が多いわけではありません。
凶を引いた場合は境内の所定の場所に結び、悪運を留めていきます。
棒は必ず元の筒に戻し、ゴミは持ち帰るなど、次の人への配慮を忘れないようにしましょう。
浅草寺のおみくじは、
平安時代の高僧・良源が比叡山延暦寺で始めた占いを伝えたとされる『観音百籤(ひゃくせん)』というスタイルです。
凶(悪い運勢)が出やすいと言われることがありますが、これは昔ながらの配分を守っているためで、特別に凶が多いわけではありません。
凶を引いた場合は
境内の所定の場所に結び、悪運を留めていきます。
棒は必ず元の筒に戻し、ゴミは持ち帰るなど、
次の人への配慮を忘れないようにしましょう。
御朱印:参拝の証し

オリジナル画像(一部生成)
御朱印は本堂西側の影向堂(ようごうどう)で受け付けています。
時間は午前8時〜午後4時30分が目安です。
御朱印は本堂西側の影向堂(ようごうどう)
で受け付けています。
時間は午前8時〜午後4時30分が目安です。
御朱印は「参拝の証」として授与される印で、浅草寺では観音菩薩の御朱印と、七福神の一柱である大黒天の御朱印の2種類があります。
受付は本堂の西側にある影向堂に設けられており、午前8時〜午後4時30分ごろまで(行事により変動あり)受け付けています。
御朱印帳(御朱印を集めるための帳面)も同じ場所で授与されています。
正しい作法としては、参拝を済ませてから受けるのが一般的です。
御朱印は「参拝の証」として授与される印で、
浅草寺では観音菩薩の御朱印と、七福神の一柱で
ある大黒天の御朱印の2種類があります。
受付は本堂の西側にある影向堂に設けられており、午前8時〜午後4時30分ごろまで
(行事により変動あり)受け付けています。
御朱印帳(御朱印を集めるための帳面)
も同じ場所で授与されています。
正しい作法としては、
参拝を済ませてから受けるのが一般的です。
お守り:種類と受け方
浅草寺では、交通安全や健康長寿、学業成就、子授けなどさまざまな種類のお守りが授与されています。
お守りの種類や初穂料(授与の際に納める金額)は季節や行事によって異なる場合があるため、授与所の係員に確認するのが確実です。
お守りは「身につけて守っていただくもの」であり、古くなったお守りは感謝の気持ちを込めて返納し、新しいお守りを受けるのが良いとされています。
浅草寺では、交通安全や健康長寿、学業成就、
子授けなどさまざまな種類のお守りが授与されて
います。
お守りの種類や初穂料(授与の際に納める金額)
は季節や行事によって異なる場合があるため、
授与所の係員に確認するのが確実です。
お守りは「身につけて守っていただくもの」
であり、古くなったお守りは感謝の気持ちを込めて返納し、新しいお守りを受けるのが良いとされています。
参拝後にみくじや御朱印、お守りを受ける際は、周囲の人の流れや係員の案内を確認し、静かに礼を尽くすことが何よりも大切です。
参拝後にみくじや御朱印、お守りを受ける際は、
周囲の人の流れや係員の案内を確認し、
静かに礼を尽くすことが何よりも大切です。
人力車・ツアー /
水上バス・ツアーはこう使う
短時間で解説と撮影サポートを受けられるのが魅力。
ただし、乗降場所・ルート・撮影対応・料金・雨天・キャンセル・保険は事業者で異なります。
短時間で
解説と撮影サポートを受けられるのが魅力。
ただし、乗降場所・ルート・撮影対応・料金・
雨天・キャンセル・保険は事業者で異なります。
浅草には徒歩散策以外にも、風情を楽しめる人力車や、隅田川をクルーズする水上バスなどのツアーが用意されています。
ここでは、それぞれの使い方や注意点をわかりやすくまとめました。
浅草には徒歩散策以外にも、
風情を楽しめる人力車や、隅田川をクルーズする
水上バスなどのツアーが用意されています。
ここでは、それぞれの使い方や注意点をわかりやすくまとめました。
人力車・ツアー:
30分から気軽に江戸情緒を満喫
仲見世や浅草寺周辺では、観光人力車の周遊コースが複数用意されています。
たとえば、観光情報サイトによると30分コース(2名)で約9,000円が目安で、短いコースや長いコースも選べます。
車夫(しゃふ)が浅草の歴史や見どころを説明してくれて、写真撮影にも協力してくれるため、初めて浅草を訪れる人にも人気です。
仲見世や浅草寺周辺では、
観光人力車の周遊コースが複数用意されています。
たとえば、観光情報サイトによると
30分コース(2名)で約9,000円が目安で、
短いコースや長いコースも選べます。
車夫(しゃふ)が浅草の歴史や見どころを
説明してくれて、写真撮影にも協力してくれる
ため、初めて浅草を訪れる人にも人気です。
- 『コース選び』
雷門〜浅草寺周辺を巡る短時間コース、隅田川沿いを回る中距離コースなど、複数のコースが用意されています。
所要時間と料金は会社ごとに異なります。 - 『事前予約』
繁忙期は待ち時間が発生するため、公式サイトや電話で予約をしておくと安心です。
乗車場所や集合時間も確認しましょう。 - 『乗車時のマナー』
車夫の案内に従い、途中で立ち止まったり撮影する際は周囲の歩行者に配慮します。
雨天時は運行中止やルート変更があるため、事前に問い合わせると良いでしょう。
- 『コース選び』
雷門〜浅草寺周辺を巡る短時間コース、
隅田川沿いを回る中距離コースなど、
複数のコースが用意されています。
所要時間と料金は会社ごとに異なります。 - 『事前予約』
繁忙期は待ち時間が発生するため、
公式サイトや電話で予約をしておくと安心です。
乗車場所や集合時間も確認しましょう。 - 『乗車時のマナー』
車夫の案内に従い、途中で立ち止まったり
撮影する際は周囲の歩行者に配慮します。
雨天時は運行中止やルート変更があるため、
事前に問い合わせると良いでしょう。
下表は、すべて各社の公式サイトや正規の予約ページへのリンクです。
電話やメールでの予約が中心の会社もあるため、最新の予約方法や空き状況はリンク先でご確認ください。
下表は、すべて各社の公式サイトや
正規の予約ページへのリンクです。
電話やメールでの予約が中心の会社もあるため、
最新の予約方法や空き状況はリンク先で
ご確認ください。
| 人力車会社 | 予約方法・公式URL | 根拠 |
|---|---|---|
| 東京力車 (Tokyo Rickshaw) | Web予約ページ:https://tokyo-rickshaw.tokyo/reservation ページ内にオンライン予約フォーム(Asoview経由)と電話番号が記載されています。 | 公式ページには「WEB予約」の案内があり、予約サイトへのリンクが掲載されています。 |
| くるま屋(kurumaya) | Asoview予約ページ:https://www.rickshaw-asakusa.com/ コース選択と空き状況確認ボタンがある予約ページ。 | くるま屋公式サイトの「WEB予約はこちらから」ボタンがAsoviewの予約ページへリンクしており、各コースと料金が確認できます。 |
| えびす屋(Ebisuya)浅草店 | プラン紹介ページ:https://www.ebisuya.com/asakusa/course/ コース一覧と料金が記載され、ページ下部に予約用リンク(WhatsApp)があります。 | 公式サイトでコースと料金を紹介し、予約はページ内の連絡先リンクから行うよう案内されています。 |
| 福ろう屋 | 予約サイト:https://fukurouya.co.jp/ 公式サイトの「ご予約はこちら」からリンクされているオンライン予約ページ。 | ふくろうや公式ページに電話番号と予約用リンク(urkt.in)が明記されています。 |
| 時代屋 | 公式サイト:https://jidaiya.biz/ お問い合わせ・予約フォーム:https://jidaiya.biz/contact-rickshaw ページ内に電話予約(03-3843-0890)案内と問い合わせフォームがあります。 | 公式サイトの人力車ページでは「お急ぎの場合は電話で予約」と記載され、問い合わせフォーム経由で申し込めるよう案内しています。 |
| 松風(Matsukaze) | RESERVA予約ページ:https://reserva.be/matukaze 公式サイトからリンクされるオンライン予約ページ。 (各コースと料金を選択可) | matsukaze公式サイトの「ご予約」ボタンからRESERVAの予約ページに遷移し、コースを選んで予約できます。 |
| 松武屋(しょうぶや)/浅草4028 | 予約案内ページ:https://ryogoku4028.com/ 電話予約(03-5830-9822/090-7948-5353)とメールフォームの案内があります。 | 松武屋の公式サイトで予約方法として電話番号やメールフォームを案内しており、このページが受付窓口になっています。 |
水上バス・ツアー:隅田川から東京を眺める
浅草からは、東京水上バス(TOKYO CRUISE)の船に乗って隅田川を下るツアーもおすすめです。
公式サイトでは、浅草発→日の出桟橋行きの片道は約40分で、通常の船は大人1,000円・子供500円、展望船「HOTALUNA」利用時は大人1,400円・子供700円となっています。
船上からは東京スカイツリーやレインボーブリッジなどを眺められ、移動手段と観光を兼ねられるのが魅力です。
浅草からは、東京水上バス(TOKYO CRUISE)
の船に乗って隅田川を下るツアーもおすすめです。
公式サイトでは、
浅草発→日の出桟橋行きの片道は約40分で、
通常の船は大人1,000円・子供500円、
展望船「HOTALUNA」利用時は大人1,400円・
子供700円となっています。
船上からは東京スカイツリーやレインボーブリッジなどを眺められ、
移動手段と観光を兼ねられるのが魅力です。
- 『乗船場所』
浅草船着場は吾妻橋近くにあり、チケット売り場で発券します。
乗船前に運行状況や混雑具合を公式サイトで確認してください。 - 『経由地を選ぶ』
日の出桟橋のほか、お台場海浜公園や豊洲などに立ち寄る航路もあります。
所要時間や料金は行き先によって異なります。 - 『天候に注意』
悪天候や高波の場合、運航が中止されたり航路が短縮されることがあります。
- 『乗船場所』
浅草船着場は吾妻橋近くにあり、
チケット売り場で発券します。
乗船前に運行状況や混雑具合を
公式サイトで確認してください。 - 『経由地を選ぶ』
日の出桟橋のほか、お台場海浜公園や豊洲などに立ち寄る航路もあります。
所要時間や料金は行き先によって異なります。 - 『天候に注意』
悪天候や高波の場合、
運航が中止されたり航路が短縮されることが
あります。
下表は、隅田川で水上バスやクルーズツアーを提供している主要会社と、その予約・問い合わせ先をまとめたものです。
各リンクは公式サイトまたは公式が案内する予約ページに対応しています。
下表は、
隅田川で水上バスやクルーズツアーを提供している
主要会社と、その予約・問い合わせ先をまとめたものです。
各リンクは公式サイトまたは公式が案内する
予約ページに対応しています。
| サービス名 | 予約・問い合わせ用ページ | 備考 |
|---|---|---|
| TOKYO CRUISE(東京水辺ライン) | オンライン予約ページ | 公式サイトでは乗船日の前月1日から出航5分前までオンライン予約ができ、事前予約で優先乗船サービスが受けられます。 |
| 東京水辺ライン(東京都公園協会) | 水上バス案内ページ | 個人利用は当日船着場で乗船券を購入。団体(15名以上)は6か月前から電話予約が可能で、無人桟橋では船内で現金購入と案内されています。 |
| Tokyo Waterways(東京ウォーターウェイズ) | 公式サイト | サイトのフッターに電話(03‑6659‑2580)、FAX、メールアドレスが記載されており、詳細・ご予約は同サイトから問い合わせるよう案内されています。 |
| Urban Launch(アーバンランチ) | 公式サイト | 定期便は予約不要で、時刻表どおりに運航すると記載。チャーター利用などはサイト内の問い合わせ先から連絡するよう案内されています。 |
| 日本橋クルーズ | 日本橋クルーズ公式サイト | サイト上に「インターネット予約」や「予約状況確認」のリンクがあり、オンラインで空席状況を見て予約できます。 |
これらのページから、希望のルートや日程に応じた予約や問い合わせが可能です。
予約の可否や運航状況は時期により変更される場合があるため、最新情報は各リンク先でご確認ください。
その他のツアー:ガイド付き散策や体験プラン
浅草では、英語や多言語対応のガイドツアーや、着物体験・人力車とセットになったプラン、和菓子作りや落語鑑賞を組み合わせたツアーなど、さまざまな体験型プログラムが提供されています。
ツアー会社や観光案内所の公式情報を確認し、興味に合ったプランを選びましょう。
浅草では、英語や多言語対応のガイドツアーや、
着物体験・人力車とセットになったプラン、
和菓子作りや落語鑑賞を組み合わせたツアーなど、さまざまな体験型プログラムが提供されています。
ツアー会社や観光案内所の公式情報を確認し、
興味に合ったプランを選びましょう。
- 『料金・所要時間』
ツアーの内容によって価格帯は1,500円〜数万円まで幅があります。
申込み時に料金に含まれる内容(ガイド料、食事、体験費用など)を確認してください。 - 『言語対応』
英語や中国語に対応するツアーも多いですが、日本語のみのプランもあります。
希望の言語がある場合は予約時に確認しましょう。 - 『集合場所とキャンセル規定』
集合場所が複数設定されている場合もあります。
キャンセル料がいつから発生するかも事前に把握しておくと安心です。
- 『料金・所要時間』
ツアーの内容によって価格帯は
1,500円〜数万円まで幅があります。
申込み時に料金に含まれる内容
(ガイド料、食事、体験費用など)
を確認してください。 - 『言語対応』
英語や中国語に対応するツアーも多いですが、
日本語のみのプランもあります。
希望の言語がある場合は予約時に確認しましょう。 - 『集合場所とキャンセル規定』
集合場所が複数設定されている場合もあります。
キャンセル料がいつから発生するかも
事前に把握しておくと安心です。
人力車や各種ツアーを上手に使えば、浅草の楽しみ方がぐっと広がります。
いずれも公式サイトや運営会社の情報を確認し、事前予約や当日の運行状況を把握してから参加しましょう。
人力車や各種ツアーを上手に使えば、
浅草の楽しみ方がぐっと広がります。
いずれも公式サイトや運営会社の情報を確認し、
事前予約や当日の運行状況を把握してから参加しましょう。
浅草では、
無料の英語ガイドから
着物レンタル&人力車セット、
和菓子作り体験、英語落語の公演まで
多彩なプランがあります。
活用の際は、ぜひ参考にしてみてください。
『その他のツアー・体験プログラムまとめ』では、これらを一覧表で詳しく紹介しているので、
下記のボタンから興味がある方はぜひ併せてご覧ください。
FAQ(よくある質問)
Q1. 所要時間の目安は?
A. 王道ルートは約60分。撮影や御朱印の待ち時間で前後します。混雑が苦手なら早朝がおすすめです。
Q2. 御朱印はどこで受けられますか?
A. 授与所の場所・受付時間・初穂料は時期で変動します。浅草寺公式で当日確認してください。
Q3. 撮影はどこまで大丈夫?
A. 掲示の撮影可否に従います。参拝の妨げになる立ち位置・声量は控え、商用撮影は申請が必要な場合があります。
Q4. 雨の日の回り方は?
A. 屋根区画のショートカットで移動し、前景小物を活かした近距離構図に切り替えると映えます。
まとめ
- 迷わない導線は「雷門 → 仲見世 → 宝蔵門 → 本堂 → 五重塔 → 浅草神社」。
- 撮るコツは前景の和小物+スマホ3Tipsで、混雑でも“整う写真”に。
- 前もって訪問日時と最寄り出口を決め、授与・撮影の可否を公式サイトで最終確認→地図アプリにルート保存しておくと当日スムーズに行動できますのでおすすします。
関連情報
- 浅草寺 公式サイト(最終確認:2025-10-28)
- 台東区/東京都観光 公式(最終確認:2025-10-28)
- 交通機関 公式(路線・出口・バリアフリー)(最終確認:2025-10-28)
- 人力車 公式/周遊ツアー 公式(最終確認:2025-10-28)
今回も最後までご愛読いただきまして、ありがとうございました。🙇🏻♂️
少しでもご参考になっていただけてましたら幸いです。
大変恐縮でありますが、心の優しい読者様が
本記事を見て参考になったよ!
と感じていただけましたら、
ぜひ下記にある『人気ブログランキング』から応援をしていただけますと嬉しいです。
皆様の些細な応援だけでも、お役に立つ記事執筆の励みになります。
どうか応援の程、宜しくお願い致します。🙇🏻♂️



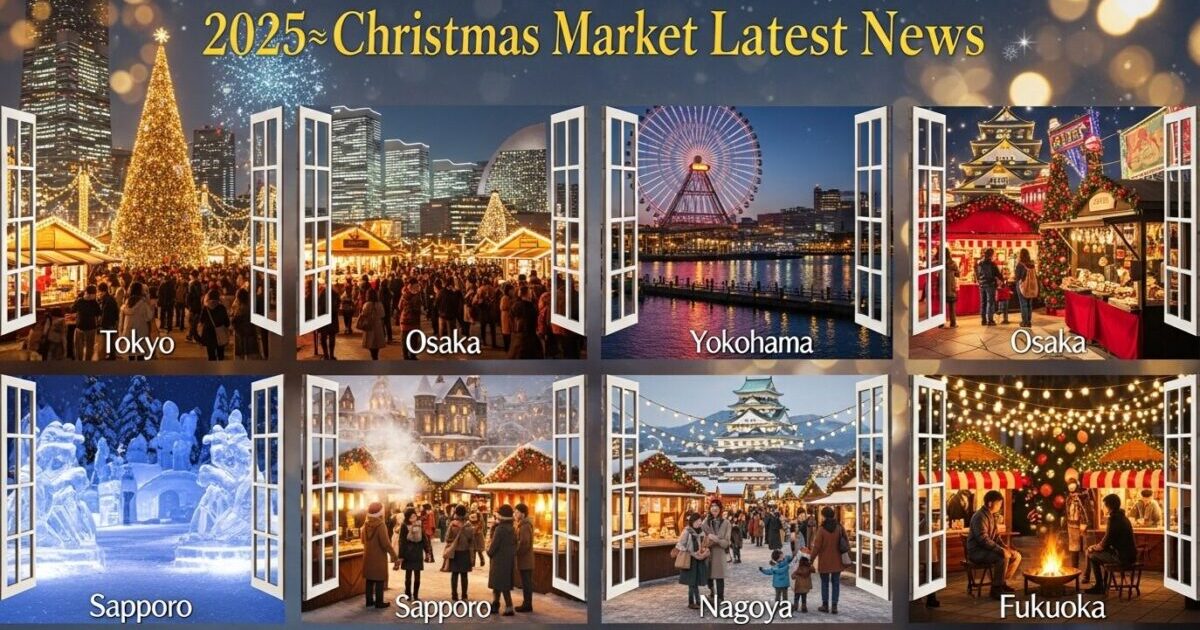
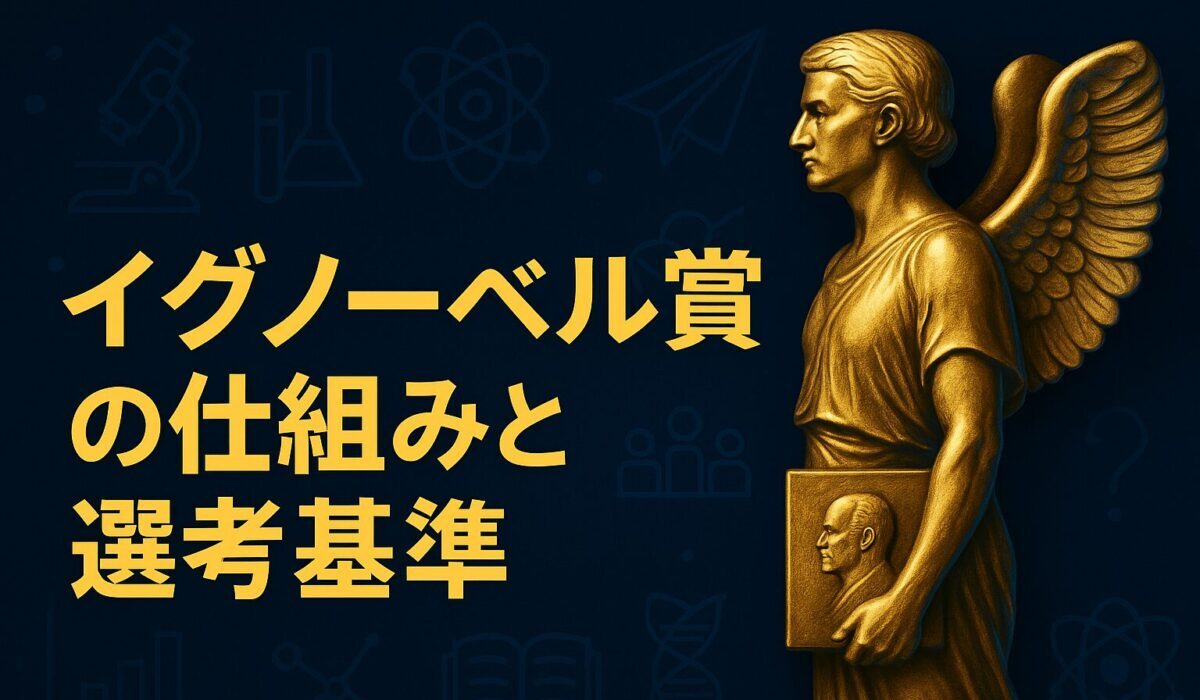









コメント